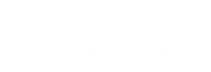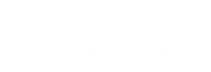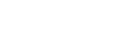
チョコ不使用なのにしっかりチョコ味。混ぜてレンチンするだけの「米粉ブラウニー」
ダイエット中にお菓子はNG? いいえ、そんなことはありません。今回ご紹介するのは、インフルエンサー・naoさんによる、混ぜてレンチンして冷やすだけと驚くほど簡単でヘルシーな米粉ブラウニーのレシピ。罪悪感のないおやつを食べたい方におすすめです。

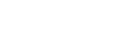
ダイエット中にお菓子はNG? いいえ、そんなことはありません。今回ご紹介するのは、インフルエンサー・naoさんによる、混ぜてレンチンして冷やすだけと驚くほど簡単でヘルシーな米粉ブラウニーのレシピ。罪悪感のないおやつを食べたい方におすすめです。




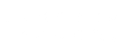




自分にもあの人にも、ワクワクするご褒美を

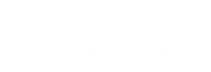
ROOMIE × パトリックステファンによる「Migaru-BAG プロジェクト」の第二弾として、2月に販売が開始された「Migaru TECH-BAG」。読者の皆さまに興味を持ってもらえるかをドキドキしながら見守っていたのですが、発売から約1ヶ月で全色完売となりました!そうした好評やリクエストを受けて、このたび「Migaru TECH-BAG」の再販を決めました!パトリックステファンに再生産を進めてもらっており、5月頭を目途に在庫が復活する予定です。